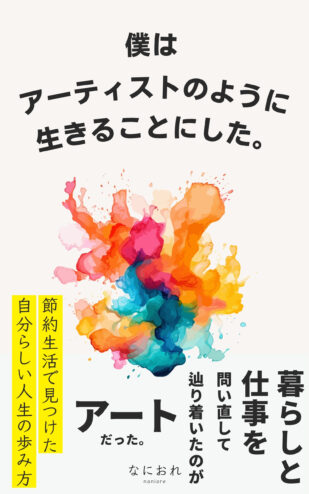
※Kindle Unlimited読み放題対象です
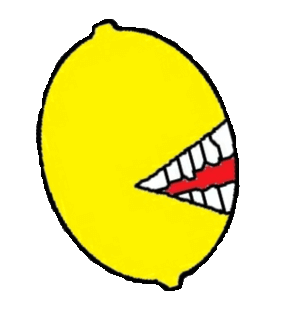

実際に使用した商品・サービスのみを紹介しています。アフィリエイト広告を含みます。
原価計算を勉強する意味って?おすすめの本は?
そんな疑問に答えます。
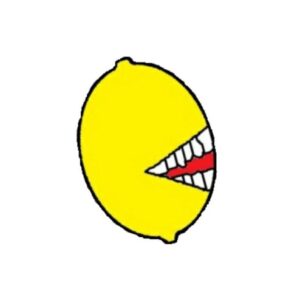 なにおれ
なにおれこんにちは、なにおれ(@lemologue)です。以前に製造業の原価計算に関わる仕事をしていました。
未経験で工場原価を扱う職種に転職したことがあり、その際に原価計算やコストダウンの本を読み漁りました。
直接的に実務には活かせませんが、原価低減の知識があるのとないのとでは全然違います。
というわけで本記事では、製造業で働いている文系が原価計算を勉強したほうがいい理由、原価計算のおすすめ本を紹介します。


「原価計算なんて経理の管理会計担当だけが知っていればいい」
と思うかもしれません。
ですが、製造業というのはすべてが工場と繋がっているので、すべての部署が知っておいて損はなりません。
製造業の営業というと、ものを売るというよりも、納期の調整や会社として販売計画を策定するための情報収集などがメインに業務になったりします。
いわゆる営業のようにものを売らないので、「自分の仕事がなんの意味があるのか」と疑問に感じることもあります。
しかし、工場原価の仕組みを知っていれば、納期調整や販売の見通しの精度が、どれほど製造原価に影響を与えるかを知ることができます。
調達の主な業務といえば、仕入先との納期調整や仕入先の工場改善指導といったことがあります。また、新規仕入先の開拓、購入方法の検討などもあると思います。
現代の製造業においては、製造原価のほとんどを材料費を占めています。
つまり、調達部の活躍が企業の利益を押し上げることに繋がるわけです。
そのため、原価計算を学ぶことで、自分の業務が原価にどれほどのインパクトを与えるかを知ることができます。
実務の原価計算の本だけでなく、コストダウンの本も読むと知見が広がります。
直接労務費と間接部門における一般管理費を同列の労務費として扱うなど、従来の原価計算とは違った考え方をすることで、適切な原価計算の方法を知ることができます。
とはいえ、企業の中で新しい原価計算の仕組みを取り入れることは難しいので、勉強したところで実務に直接は活きてこないと思います。
ですが、幅広い考え方ができることには間違いなく価値があります。
原価計算を学ぶことで、生産の平準化におけるヒントや在庫に対する正しい知識と可能性に気がつくことができます。
また、工場管理のような工場の生産をサポートする業務も含んでいれば、現場でのカイゼンが生まれる仕組み作りや、経費の削減などの見方を身につけられます。
ものの受注から生産までにおける一連のプロセスが、製造コストにどのように紐づくのかを理解することで、広く会社における必要な人材を考えられるようになます。
製造業の人事で、現場のことがわからないのは致命的。
製造業の人事としてキャリアを形成したい人は、原価計算やコストダウンの本を読むべきです。


結論からいえば、こちらの6冊です。
「原価計算だけで満足していませんか!」では、開発、設計、生産技術、購買、生産管理、原価管理、経理、営業、製造など、あらゆる部署目線での原価に対するあるべきスタンスが記されています。
内容も非常に読みやすいです。
細かい実務の話はありませんが、「どういったことを考えながら業務をすると利益に繋がるか」の気づきがある本だと思います。
一貫して書かれているのが、現場での現地現物の確認になります。
文系でデスクワークで働いている人にとって現場に足を運ぶのは億劫に感じると思いますが、この機会に考えを改めてもいいかもしれません。
「「原価計算」しているのに、なぜ「儲け」が出ないのか」は、ABC(活動基準原価計算)について、ストーリーテイストで分かりやすく書かれています。
登場人物が動くので、小説を読んでいるように楽しめます。
全部原価計算では間接費が一定の定義に基づいて配賦されるのに対して、ABCは間接費の配賦を製品別などで出来るだけ正確に原価計算を行います。
製品別の原価計算が正確に行えることで、利益に繋がる原価管理に繋がります。
企業の1担当が会社の仕組みを変えたりするのは非常に骨が折れると思いますが、普段の業務の中で感じた違和感(もっとこうすれば正確な原価になるのでは…?)といったところの疑問がクリアになるかもしれません。
こういった知識は知ることが大事なので、ぜひ読んでみてください。
「モノづくりを支える「管理会計」の強化書」の想定の読者層は技術者となっていますが、直接部門も間接部門も知っておいたほうがいいことを学べます。
技術屋さんは、「なにをどうすれば利益に繋がる設計ができるのか」といった知識を得られます。
会社における設備投資や間接部門の人間の労務費の位置づけや、過去と現在のメーカーにおけるコストの考え方を知るのに最敵な1冊です。
「誰も教えてくれない「工場の損益管理」の疑問」は、個人的に1番学びのあった本です。
私の仕事は、工場の改善促進やお金の管理を司る業務を行っていますが、実際に自分でコストダウンを図れることはなく、他部署に協力してもらうことになります。
製造目線だけでなく、営業などの他部署からの目線も書かれているため、製造業で働く文系の方は、自社の製品のコストに普段の自分の業務がどう紐付いてくるのかのヒントが得られると思います。
「原価計算の本質と実務がわかる本」は、実務的な本です。
製造業で働いている以上は営業などのものを売る部門でも、自社製品のコストがどのように決まっているかは知っておいたほうがいいです。それに、コストの知識を有する営業は、非常に頼りがいがあるように見えます。
本の内容としては、かなり堅苦しい会計本となっていますが、この1冊を読むだけでも、社内でもトップクラスの知識量になると思います。
「最強のデータ分析組織」は、大阪ガスのデータサイエンティストについての本です。
原価計算に関する本ではないのですが、製造業で働く上では、現場に足を運ぶことがいかに重要かを知ることができます。
バックオフィスで仕事をしていると、工場の現場や販売の現場に足を運ぶことはまずないでしょう。周りをみてもそんなことをしている人もいなければ、教えてくれる人もいません。
ですが、バックオフィスの方が現場に足を運ぶようになれば、部署の中では間違いなく最強の人材になれます。現場を知っているか知っていないかの差は、びっくりするほど大きいです。
製造業で働く文系におすすめの原価計算の本を紹介しました。
本記事で紹介した本は、製造業で働いている自分の仕事が、会社にどう役立っているのかが見える本でもあります。
仕事へのモチベーションに繋がったり、部下の指導に論理的に業務の説明ができたりするようになるので、すべて一読することをおすすめします。
▼関連記事


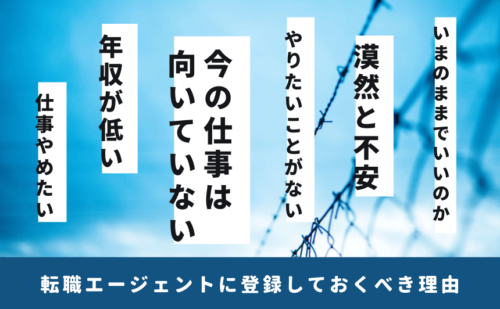
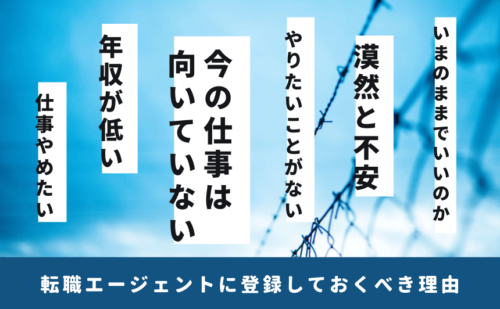
以上
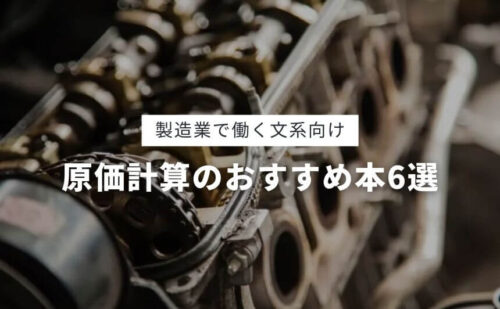
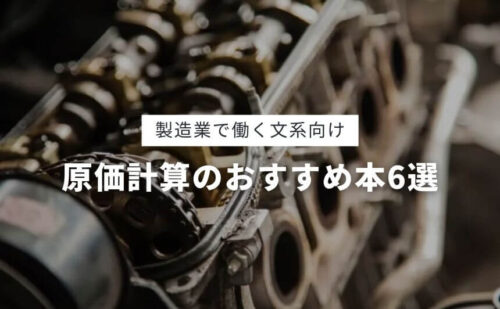
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
なにおれKindle本「生きづらい人のためのシリーズ」を公開中
本書は、「生きづらさを抱える人が、生きづらさから抜け出し、最後には自分だけの生きる意味を見出すまでの道のり」を、全10のステージで解説しています。
いってしまえば、"生きづらい人に特化した超実践的な生き方の指南書" です。